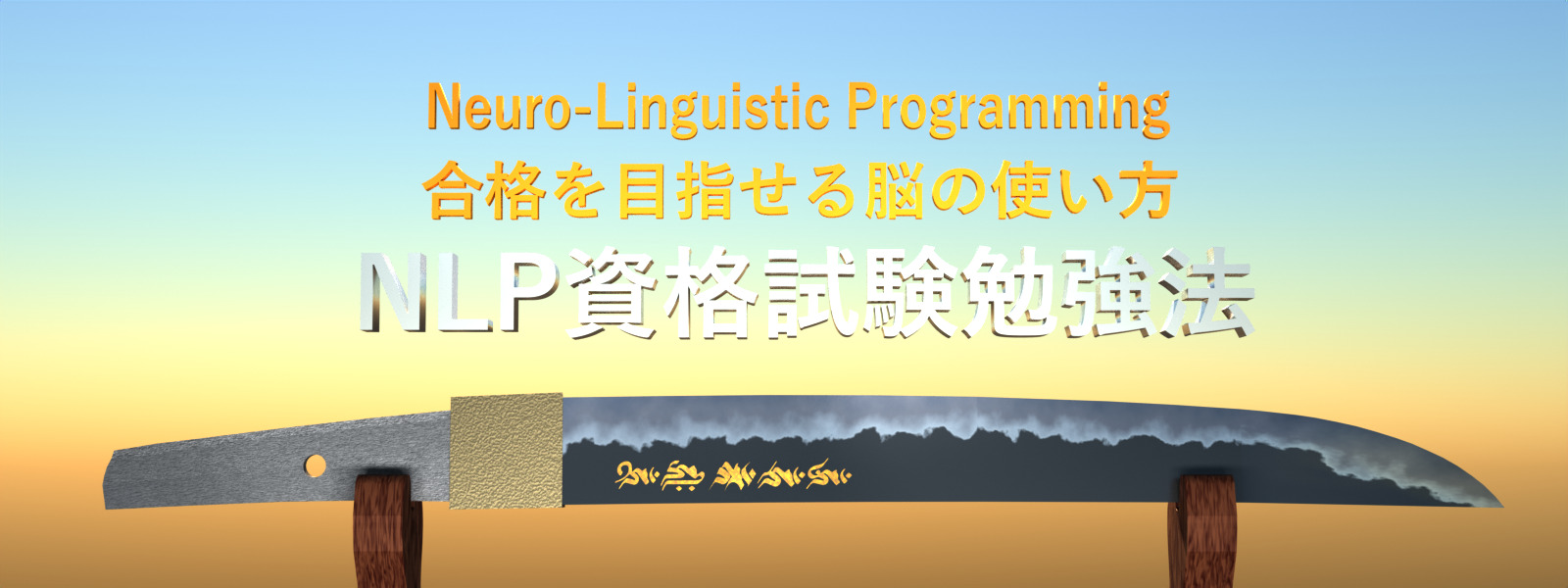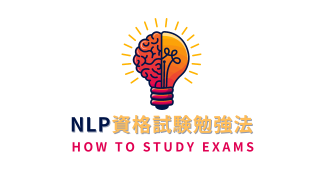「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年5月16日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
連休中に遅れた勉強を挽回する実践はどうですか
こんにちは近藤哲生です。前回、上の実践を提案をしました。それが特に不得意科目の過去問を高速に周回してそのデシラ(試験に頻出でも自分が解き方を知らずに誤答することで受験科目に設定された合格基準の未達つまり不合格を招来する要因)を解消する勉強。これによっで追い込み期を有用に使えるようになるからでした。
それを有用に使える理由は不得意科目で不合格になる怖れを低減することで得意科目の得点力を向上させるの勉強にも励める。更に不得意科目の過去問、その得点力をギリギリの状態から総点を高められる得意科目的な状態に向上する。その双方からして、余裕で合格を目指せる追い込み期の有用な勉強ができる事でした。
5月中旬の理想と現実のギャップ
その一方この時期、連休の喧噪も終わり勉強にも打ち込める頃。朝夕の気候は寒からず暑からずカラッとして実に快適。学習の集中力を下げることもない。勉強の秋とともに合格を目指す学習に理想な時節はず。だがその現実はどうだろうか?仕事は多忙さを増す一方、五月病でなくても試験勉強の伸び悩みなどにも直面する頃かもしれない。
その伸び悩みは勉強に限らずある現象だが次のよう悩みだ。
「今のままじゃ合格する自信がない」
「何を勉強しても合格する自信を持てなわ」
「覚えたはずの要点を忘れて本試験に自信がないよ」
勉強をするからこその嘆きだがこれを放置するのはどうだろうか?
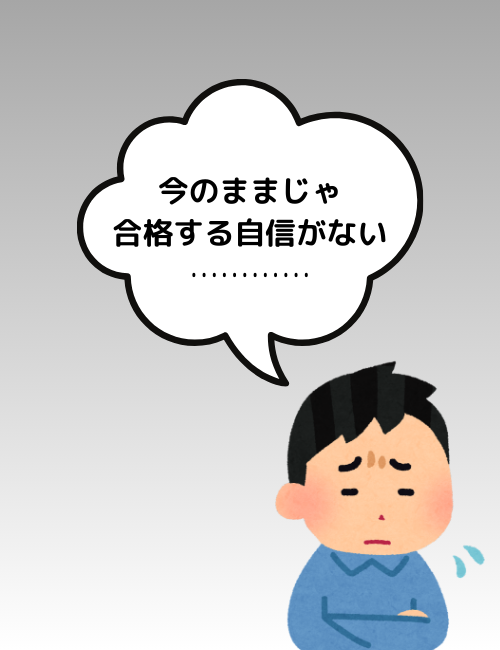
その内なる声は、これを発言としてSNSで漏らさずとも、折に触れて自分に囁きかける。不得意科目の克服で過去問の周回をしている時、得意科目で総点を稼げる仕上の勉強をしている時、または勉強の休憩の時などに気に障る雨だれの様に心の中で語りかける。先の様な悩みや嘆きを実際に独り言にもしているかもしれない。
自信のなさをどう解消するのか
そうだとする、前述のような鬱陶しい心理状態にどのように対処すれば良いのだろうか。仕事も忙しく勉強は追い込み期、この時期に心理療法などを受けられる暇もない。お悩み解決本をネットでポチり一読しても隔靴掻痒で終わる。時間を浪費してSNSに救いを求めても「大丈夫だよ」と無根拠の励ましが返るだけ。
自己啓発界隈に詳しい方なら例えば「私は合格できる」「私は自信に満ちあふれている」等と実際に自らに対して肯定的な宣言をするかもしれない。しかし、そうする人もその内心は「それで不得意科目、計算問題の得点を取れれば何も心配しないわ」と本音を吐露するのが実情では。自分の事は自身が正直に知っているのだから。
そもそも合格を目指している受験生は一所懸命に勉強したい時期にそれらの事をしている暇を有していない。そうだとするならば、合否にも影を落とす自信なさげな状況に対して合格を目指している受験生ができる効果的な自助努力とはどのようにすることか。今回は試験本番にも効力のある自信を培う実践をご案内したい。
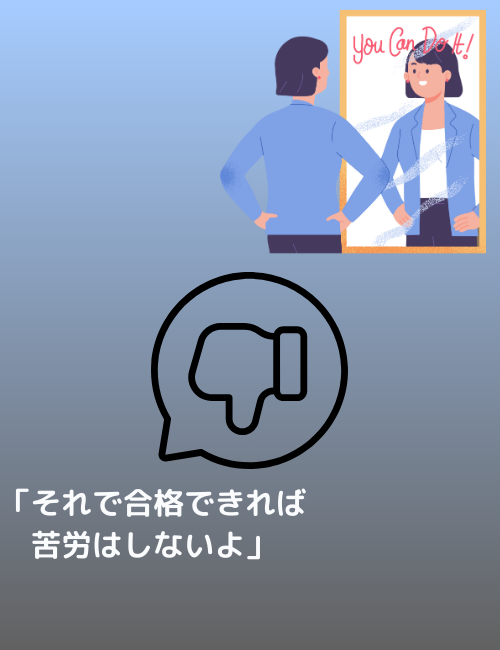
結 論
その方法は啓発本もセラピーも不要。小さな成功体験の着々とした積み重ね。小さなことはやれば必ずできる単位の対象だ。これを行ったつまりやればできたその結果を1つ1つ蓄積する行為だ。加えてその行為と結果を自ら対して明確に認知させる為にそれらの記録(いわゆるジャーナル)を行う。そして時に読み返す。
その着々とした積み重ねは「それで自信がつくって怪しい」とも評される。しかしその声はその小さなことを行うもせずに発せられている。小事、例えば天災でも無い限り実行可能な約束として「○時に行くね」としながらもお決まりのように遅刻する。急な仕事の依頼が無い限りやればできる経費精算を先延ばしにする。
その不能的な経験も優秀な人脳は確実に学習する。低強度のような経験でもこれの繰り返しにより確実に学習の強度を高める。前述した私事や仕事でのこれを繰り返そうが取るに足りないと表層意識が断じる。だが「やればできることをやらなかった」経験を「やればできることもできない」と一般化した深層記憶として保持する。
表層意識と深層意識の力関係は意識と無意識の力関係として知られる。その合わせた力を百%として前者が数%後者が残り殆どを有する。よって上記の記憶は事ある度に「できない・やれない・無理」とする自信のなさとして自らを拘束する。こうした意識構造からして、小さなことを疎かにする行為はやがて自らへの呪いとなる。

小さな成功体験は「やらなくても良くネ」としがちな小事でもこれをやることで「これもできた」体験だが、これを積み重ねることも上記の学習を形成する。但し前述した否定的でなく肯定的つまり有用な「私はできる」と一般化された記憶を確立する。即ち自らに対する祝福として機能する。結果的に凡事徹底の効力を発揮する。
凡事徹底と小さな成功体験の鏡像関係
凡事徹底を「年寄りお得意の4文字熟語~」と感じるだろうか。そうであっても実際に成功者達はこれを実践する。その典型が大谷翔平選手だ。彼は打者についた際に塵を拾う凡事を徹底する。控えにあっては床に散らかった塵を以下同文。加えて周囲に対して挨拶や気づかいを表す凡事徹底ぶりだ。その結果はご存知の通り。
凡事(なんでもない当たり前のこと)即ちやれば必ずできることを徹底して行う行為はこの成功の規模を問わずに蓄積される。深層意識に於いて強力な潜在能力となり現実に効力を発揮する。これを彼のみならず成功者達は熟知している。逆に凡人はそれを疎かにするが故に自らを非力や自信のなさに導き自らを凡人たらしめる。
ひいてはその関係は自ずと試験勉強にも適用できる。合格者はこれになる前に自らに於いて何でもない当たり前に思える得意科目の過去問を徹底して周回つまり極めた。不得意科目の過去問は「今夜は○問ならやれば解けるな」と何でもない当たり前に思えるようにこれを細分化してこれを解くという凡事を徹底する。
小さな成功体験にあるあるな勘違い
その事実に対してありがちな声は「ケドそうしても正解できなきゃ意味なくない」と言う。確かに正答を目指して周回する勉強が合格を目指す為に資する。だが仮に誤答したとしても「やると決めた事をやれた」という小さな成功体験があったのは事実だ。それが繰り返されることは深層意識にやればできる事実を刻印する。
その刻印を一概に自信と呼称するが、その1つを自己効力感と言う。これは何かを上手くやれる見通し即ち何かを上手くやれる自信を意味する。その自己効力感を養うことに仮に誤答したとしてもやればできる勉強を繰り返すことが前述した深層意識の構造からして極めて有用。かつ誤答は正答をもたらす不知の知を賦活する。

その誤答は「また間違った」と自己批判も誘発するが「これは学び直しの好機」であることも意味している。結果的に不合格になる者をして「オレ・アタシって駄目」と暇な自己憐憫をさせるが、やがて合格する者をして「これが正答できるように勉強できたら良いよね」と強い学習の動機づけをしさえする。このように見方次第だ。
自己効力感を培う必要性
これはひとえに受験本番で合格を目指せる実力発揮にある。その本番で設問を目前にして「これって正答できそう」と上手く解ける見通しつまり自信を覚えられる自分になる為だ。想像すれば解る事だが、仮にその状況で「これって無理」と思った瞬間に想起できるはずの正答に役立つ解法も想起し難くなる。
その訳は私たちが自己予言に拘束される特質に由来する。「やれないはず、できないジャね」と迂闊に予言したことで人は自己暗示に陥る。むしろその言葉を証明しにかかる。結果、「ほら言ったとおりジャン」と安心する。度し難い即ち痛い習性を手放さない。だから合格者達はその習性を逆活用できるように凡事徹底をする。
以上をまとめる。小さな成功体験の着々とした積み重ね、例えば不得意科目で特に繰り返して誤答した過去問を取り組めば必ず解けるように細分化した問題数にしてこれはやれば解けるのだから、そのように必ず行う。誤答した結果は再学習の好機にして正答の糧にする。この実践を深層意識に1行日誌なども使って着実に蓄積する。
その結果は本試験に於いて絶大な効力を発揮する。例えば配布された試験問題集をめくって次々と目に映る設問に「これって解ける」と自信、自己効力感を覚えられる。設問によっては見た瞬間に正答となる選択肢を言い当てることが可能だ。合格まで長期を要した勉強嫌いの私にですら先の実践はその実感を与えたのでした。
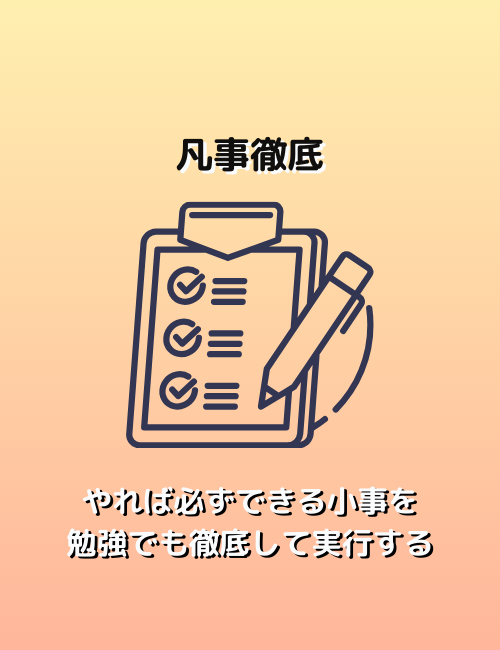
勉強での凡事徹底にも健闘を祈る
GoodLuck!