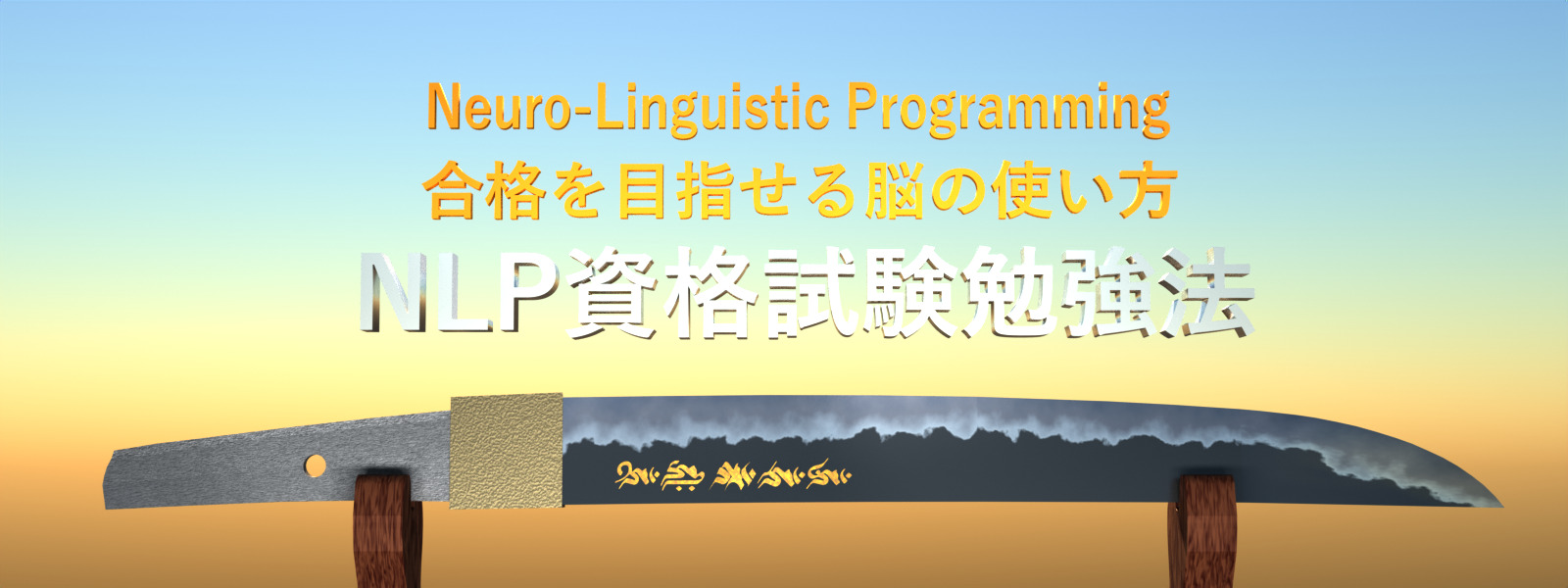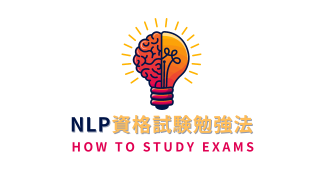「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年4月25日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
テスト中心の勉強ってどんな調子ですか
こんにちは近藤哲生です。前回、上記のご提案をしました。その提案を実践された場合、過去問の組み合わせで設問の8割前後を出題する資格試験の特質と過去問の正答に資する情報を想起することが学習者の記憶を強化する脳神経機構から、上記で過去問の解法を体得した受験生は合格点を獲得しやすくなるからでした。
他方、「それって資格試験勉強の王道かもしれないけど、過去問の解法を覚えられなくて勉強するのにウンザリ」とお嘆きの諸氏の絶えることもない。確かに、分かっちゃいるけど肝心のものを覚えられない状況は、これにある人を大いに嘆息させる。しかし、それで受験勉強が思い通りに進めば誰も苦労はしない。
藁をも掴む行為が招来する結果
そこで、溺れる者は藁をも掴む勢いで「過去問解法これだけ要点集」などと銘打ったアンチョコ本に食指を伸ばす。でも、それが述べる解法の説明にイマイチ得心がいかない。過去問集にある解答解説が述べる解法過程と同じく腑に落ちる読解ができない。で、「これじゃ最初から過去問だけにすれば良かった」と後悔しきり。
あるいは、「嫌じゃしょうがないから、過去問を繰り返して解けばそのうち解き方が分かるわ」と無根拠の期待を抱いて貴重な勉強時間を費やし続ける。そうして本試験に備え予備校などが公募する答練や模試で得点力の検証をしてみた。すると「これって全く解ってなかったってこと?!」とその期待がその得点から見事に裏切られる。
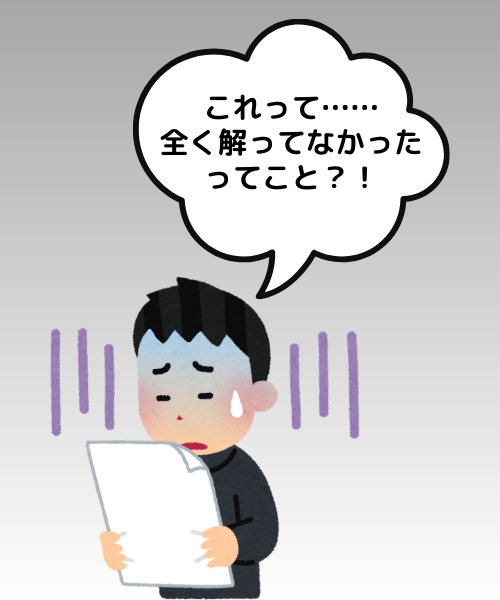
今のままで本試験に臨めない。現時点で過去問の解法を体得する方途に目処が立っていない。もしもそうした状況に貴方があるとしたら、合格水準を満たせる得点を獲得できる過去問の解法を体得できる勉強の仕方はこれをどうしたら良いのだろうか?今回は試験勉強の核心である過去問の解法を体得できる勉強法を確認したい。
結 論
それが過去問の解答解説を要約する実践。「この解法って要するに○○するのね」と事細かに記述された解答解説の文面を自分の言葉で要約つまりその要点を端的に言語化にする行為。以上の要約する過程がこれを行う学習者に読解に必要な脳機能を大いに起動させる。「解答解説がスッと腹に落ちたわ」と得心を与えるからだ。
私たちは要約を作る為に次の過程を経る。先ず要約したい文章から不要な部分や冗長な部分を削る。次に文中に出現する様々な語彙に共通する要素に着目してそれらを抽象化(上位の語彙に置き換え)した語彙でまとめる。更に文意の中核である主題文を見つける。最後に前述の抽象化した語彙と見つけた主題文を使って要約を作る。

例えば、一級建築士の令和6年度、法規7問の正答である選択肢に対して次の解答解説(引用元:「令和6年度 一級建築士 学科 過去問スーパー七」114項 発行:株式会社総合資格)がある。
「設問の建築物は主要構造部を耐火構造としているため令第百二十一条第2項に該当し、令第百二十一条第1項各号で規定する床面積は2倍の数値として適用される。令第百二十一条第1項第三号イにより、ナイトクラブの用途に供する階でその階に客席を有するものは、2以上の直通階段を設けなければならない」
上記は「令第百二十一条第2項」が二直階段で設置面積の緩和規定、「令第百二十一条第1項各号」が二直階段を設置する面積規定、「令第百二十一条第1項第三号イ」が用途による二直階段の要求、以上から「要するに『二直階段の設置』問題で面積と緩和数値と用途からこの選択肢を選ぶ」と要約できる。さてどのようにしてか。
要約の過程を俯瞰する
解答解説などを読んで解る受験生は次の過程を行う。まず文章を構成する基本単位である単語の意味やその使い方に関する理解を確認する。次に単語が担う主語や述語、修飾語に関わる語法を認知する。更に代名詞や指示語、接続語で繋がる繋がる記述を理解する。加えて既知な情報との一致を確認する。
最後に上記の過程を経て先に例示した二直階段に関する解答解説の要約が生成される。結果、「理解したかった解答解説の要点がスッキリ見えたか」などの認知に関する認知であるメタ認知が起動する。以上の過程が問題なく進行した場合、これに関わった学習者は解答解説の読解、過去問の解法に強い記憶を得られる。
しかし、それを覚えられない。即ち読解の過程に問題を孕んでいる場合、「理解したのに解答解説の要点がぼんやりしている」「その要点がシッカリ掴めない」とした否定的なメタ認知を当該の読解に支障を秘めた学習者は得るに至る。つまり、解答解説に関わる自らの読解に「オレ・アタシって読めてないかも」となる。
ではその否定的な感覚を得た場合、その状況をどのようにして打開できるだろうか。第一にその状況を得た事実は、決して悪いニュースでない。「オレ・アタシって駄目じゃね」と決して自らを叱責すべきでない。自分を責めてことが済むなら誰もが苦労はしない。自らの読解力を向上させる為に有用な良いニースなのだから。
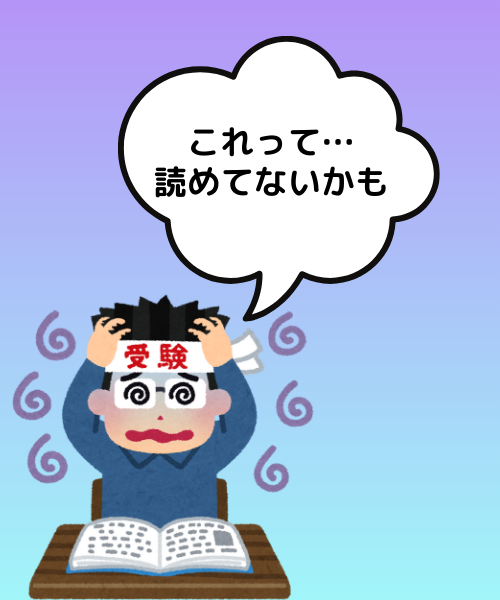
読解力の向上に役立つ実践
第二に下で列挙する項目を要約の過程で1つ1つ実行しよう。
1.分からない用語や単語の意味を明らかにする
2.単語が担う主語や述語、修飾語に関わる語法、機能を確認する
3.代名詞や指示語、接続語で繋がる繋がる記述を理解する
4.自分の既知な情報と読解内容の一致を確認する
1を求めるのは、一級建築士の受験生を例にすれば、これを必須とするが先に例示した法規だ。これは建築基準法の第二条が規定する「用語の定義」から以下に続く全ての文章を展開する。この学習者は用語の定義を不明確にした場合、当該の二条以下の法文とこれに言及する解答解説を理解できなくなるからだ。

主語や述語、修飾語の働きを認識する
2を行う訳は、例えば建築基準法にある第五十六条の二、日影による中高層あ建築物の高さ制限に存する。この条文はこの冒頭で区域の定義をした後に一般的な単語を用いて各区域つまり条件節つまり修飾節を記述する。これが主語「建築物」に係り、次に様々な単語で記述される長々しい条件節、すなわち修飾節が構成される
前述した修飾節が条文の後半にやっと出現する「しなければならない」とした述語(節)にかかる。更にこの後、「ただし」から法文末にある「この限りでない」とする述語(節)にかかる条件節つまり修飾節がクドクドと展開する。よって、これらが織りなす語法や機能を正しくを確認する行為が法文の読解に必須であることだ。
以上の主語にかかる修飾節と主語、述語にかかる条件節と述語などを明確にしてそれらの働きを認識する。そうすることで、法文の意味を心像として抱くことができる。即ち「法文のポイントが絵になった」「法文のキモがイメージできた」等と言える知覚を得る事が叶う。この法文に関わる解答解説もスルリと腑に落ちるはずだ。

代名詞や指示語の働きにご用心
3が読解者に要求者に求められる理由は、前述した2で触れたように「区域(以下この条文に於いて対象区域という)」と本条文が定義した代名詞や指示語的に機能する語彙に関することだ。その語彙の働きを把握し損なった場合に本条文の読解は不可能なこと。同じく本条文の接続語「ただし」の働きを見落とすことも同様になることだ。
4を行う理由はこうだ。例の条文は「日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない」と述語節を述べる一方、それを生じさせる部分が何かを明示しない。それが最高高さをなす建物の部分やその水平方向の幅とできる自分の既知な情報と読解しつつある法文との一致を確認することで法文理解ができることだ。
面倒な4項目がもたらす結果
以上に例示した4項目を果たす事によって、過去問の解法を体得することに不可欠な解答解説を読解する受験生は過去問解法を着実つまり「解答解説の要点がスッキリ見えた」「そのポイントがハッキリ掴めた」と言えるようなり、「この解法って要するに○○することね」と端的に過去問解法を要約できるはずだ。
読解した文章を要約できることはそうした文章を理解した事実と表裏一体である。即ちそれを理解した結果として要約が可能であり、要約が可能である事実が読解した文章を真に理解したことを担保するからだ。以上を端的に言おう。過去問の解法を体得できる勉強法は自らが要約できる様にその解答解説を読むことである。
過去問の解法を体得できる勉強法に健闘を祈る。
Good Luck!