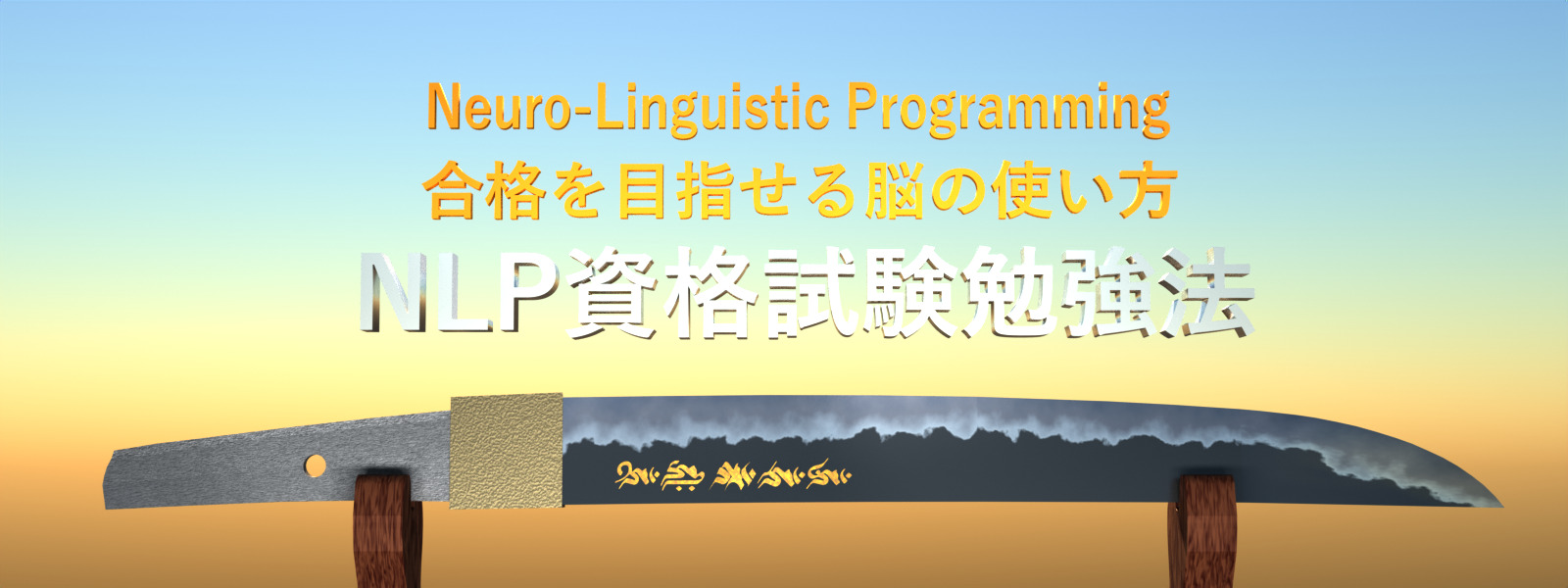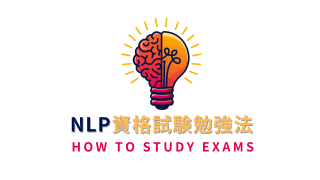「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年7月4日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
通勤路記憶法の実践はいかがですか
こんにちは近藤哲生です。前号は本質的な試験勉強法はこれを再確認しました。誤答を正答に必ず変える方法でした。合格を目指す「資格試験」の勉強でもαでありΩ。資格試験の設問は過去問の組み合わせでその8割前後が作成される。誤答した過去問を正答に転じられる能力を養えば本試験でも8割前後の得点ができるから。
では頻出の過去問題はこれに上記の勉強を適用するのは何故か。次の本試験でも同類の問題が出題される可能性がこれ故に極めて確率が高い。資格試験が有資格者たる能力の査定をする問と考えると、その過去問は合格基準の得点に直結するはず。各科目の得点に設定された合格基準を満たすことは大いに見込めるはずだ。
私が設問作成者であるならば、資格試験は有資格者的な知力を査定する機会と設定する。その査定は公平性から毎年の合否判定で一定水準を保つ。そう設定された各科目やその総点の合格基準によって毎年公平に計測できる。その公平さが通年的に均質的であるとすると、前述した頻出の過去問題があるのは自然な事だろう。
試験直前期にあるあるな本試験に対する不安
さてこの時期、次のように心が揺らぐ。
「本試験でミスするかもと不安」
「試験本番であがって失敗しそうで不安」
「本試験で実力を発揮できるかどうか不安でいっぱい」
さて、そのような不安はこれをどうしたら解消できるのか。
例えば、自らができる全てをやり尽くし、本試験前日までもそれを行うつもりの貴方ならば、万事を尽くして天命を待つことができるだろうか。勿論、「ウン、ソレキャないでしょ」と泰然自若でいられるのであれば、これから先の記事を読み進めるのはご不要。どうぞ、できる全てをやり尽くすことにご尽力下さいませ。
本試験の不安とは果たして何ものか
対して「天命なんて待てないから不安なの」とお感じであろうから、ここまで読み進めた貴方では。であるのならば、新暦の七夕に合格祈願をした短冊でも窓際に飾りますか。でも「神頼みで不安が減るなら苦労はしないわ」も本音でしょう。このAI全盛期に短冊で願いをかけるのってファンタジーと言わざる得ないのだから。
いずれにしてもその不安とは何か。確かに私たちは不安をまるでどうしようもない怪物の様に捉えがちだ。しかし本当にそうだろうか。実際に確かめて欲しい。その不安がある場所はどこか。右の人差し指と左のソレとで夫々に触れた左右のこめかみの間だ。こうして見るとたったそれだけの場にあって決して巨大でもない。
とは言え人もまた以下の様に思い込みに制約される。例えば、サーカスで曲芸を見せる巨像は自らの力で引きちぎれそうな鎖に拘束されるが決してそうして逃げない。子象の時に鎖に拘束されて自由になれなかった経験はそうなれないと言う思い込みを作る。私たちもまた試験に対するある経験から制限的な不安を作る。
ではどうしたら試験直前期にその不安の解消法できるのか。
今回は本試験に不安を減らし能力全開できる方法のご案内です。
結 論
その方法が本試験の疑似演習。つまりそのシミュレーション。要するに模擬試験だ。例えば、受験予備校をご活用でしたら、それが提供する模試をできるだけ多く体験する。そうでなく独学でしたら、本試験と同様に時間と状況の設定とをする。ランダムに選んだ真っ新な過去問に本気で真面目に合格点を目指して取り組むのです。
後に該当する方は、特に本試験と同様の状況設定を正しく行います。例えば、試験中に参照できる法令集があれば、本試験の規定通りのそれを使用する。筆記具なども同様にする。更に、スマホも使用禁止だろうから同様にそうする。勿論、BGMも本試験でないので無しにする。その状況下で任意に選んだ年度の過去問を解く。
その様につまり本試験と同様に一切の介入、例えばスマホの着信音や呼び出し音が聞こえない状況を作る。同居の人がいるならば、その人が模擬試験の場に立ち入らないようにしておく。またはその場を確保できるレンタルルームなどを活用する。いずれにしても、できるだけ本試験と同様の状況を体験できるようにする。
解答の戦略的なシミュレーションも行う
時間と空間の模擬体験をしつつ行いたいのが戦略的な模擬演習。具体的には設問の仕訳とそれに対する時間配分だ。例えば、前者は設問毎に○や△そして×を付ける。○は1問当たりA分を使って必ず点を取り、△は時間に余裕があったら1問当たりB分取り組み得点を試みる、×はこの設問の点を捨てるように仕訳する。
実際にその仕訳と時間配分を模擬演習しておく。「この時期って過去問をやり尽くしたので×問はないんジャね」と思うかもしれない。であるならば、×問を最後に正答を目指すとするのも一法だ。いずれにしても、本試験で合格を目指す為に有用だと考える自らの戦略を事前に予行演習して、その可否を試すのは大切だ。
特に苦手科目でこれを行うことは、本試験に於ける苦手科目の取り組みを改善して合格水準の得点を獲得できる経験知をこれの実践者に与える。前述のように捨て問と絶対に得点する問とを決めて取り組む経験をも得させる。残り数回の週末に戦略的な模擬演習をしておけば、試験本番でどうしようと焦ることを減らせるはずだ。
経験知で量の違いは小さいが質の違いは無限大
と聞くと「ソレってもっと前からやるべきジャね」と突っ込みたくなるだろう。確かにそうあってしかるべきだ。以前から前述したような設問の取り組みをしてきた向きならば、その取り組み自体が既に本試験対策として機能することからして(後は本試験を楽しみにして)本試験に不安を覚えることも少ないと想定できる。
しかし、多忙な毎日と尻に火がついて本気の対策ができるあるあるな人の習癖からして、「ソレって今からやらなきゃ」であるのがあるあるなこと。そうである、またはまだそうでないから、つまり何ら対策を講じていないことからして、冒頭のような不安を覚えて当然である。不安に塗れる暇があったら対策を講じるのが得策だ。
以上はどうだろうか。例えば「それだけで本試験の不安が消えるってホント?」と異論を覚えるだろうか。確かに模擬演習で得られる経験知の量的な差は0と1と言う様に実に違いは小さい。だが、それが人に与える質的な差は学習の有無が違いを創る違いとして作用する。その違いはとてつもなく大きいと言っても過言でない。
本試験のシミュレーション後に行うべきこと
本試験のシミュレーションをしたら「うん何だか本試験の不安が消えた」と安心を得たからとして、模擬演習をやりっ放しにしては決して駄目だ。やりっ放しは模擬演習の価値をドブに捨てるようなもの。そうするのではなくて、必ず行いたい事後処理が誤答した設問や捨て問した設問の解法を徹底的して体得する勉強だ。
それらの設問に関わる回答解説を読解する。解説文の用語1つ1つが有する意味を明確にする。曖昧なものはこれを調べてハッキリさせる。その一文一文の文意を正しく認識する。最後にその文全体が織りなす意味、何をどうする何故ならばと認識できる解法の論理を明確に理解する。その理解を元に解法を暗記する。
その暗記を確実にする為に1日や数日後に「必ず」「絶対に」「何が何でも」その暗記をした設問を正答を目指して解き直す。こうして誤答した設問に関わる回答解説を以下同文。誤答や捨て問が無くなるつまり全問を正答できるまで繰りかえす。即ち本試験の疑似演習の後にも本質的な本質的な試験勉強法を適用する。
以上を本試験までの週末とその後に行っては如何だろうか。七夕の短冊を窓辺に飾るよりも遙かに心を安んじてくれるはずだ。貴方の合格する可能性が天の川のように高くもなることを願って。
本試験の疑似演習にも健闘を祈る。
GoodLuck!