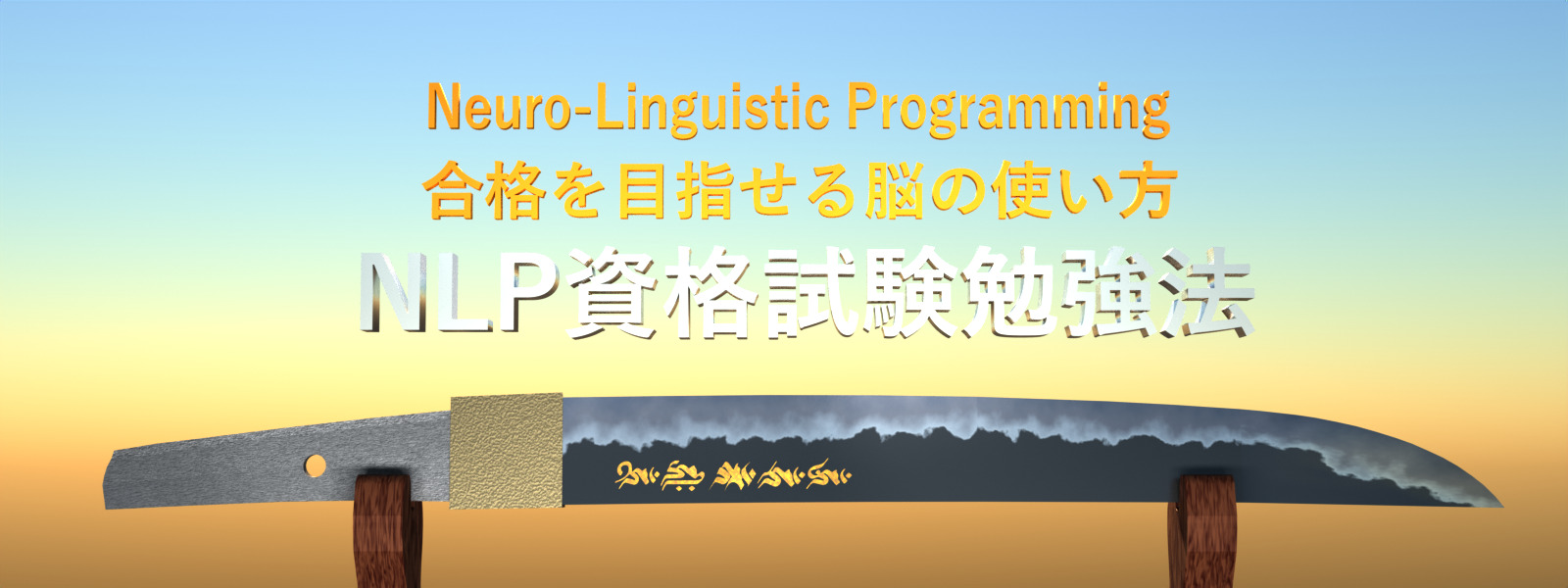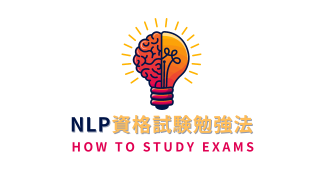「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年5月2日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
過去問の解答解説を要約するのってどんな調子ですか
こんにちは近藤哲生です。前回、上の勉強法を提案をしました。それを実践された場合、得点を取れる過去問の解法を教えてくれる先生的な存在である解答解説を理解(これは「解った」体験に基づく記憶つまり意図的に想起しやすい記憶を生成する)できる。この結果、過去問解法を体得できるからでした。どうでしょうか。
勿論、「国語じゃねーし要約するって意味ないよ」と反論もあるはず。要約ができずとも過去問の解法が丸暗記できれば得点できそうだからと。だが要約は大事。解法の要約できなければ理解が怪しい。人は解答解説の要約が可能ならその理解ができている。正しい理解を問う多くの出題をする本試験で正答ができるからだった。
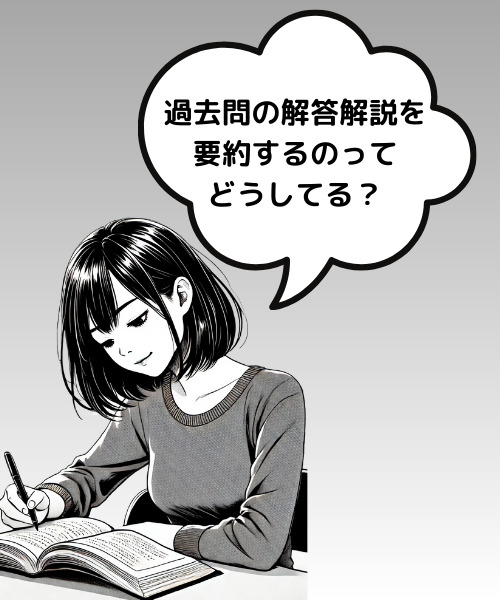
連休後半はどのような勉強をするのが得策か
いずれにしても暦は既に5月。夏期に本試験を迎える建築士や社労士などの受験生はこれから否すでに試験勉強の追い込み期にある。不得意科目を科目の合格基準が満たせ、かつ得意科目を総点の合格点を満たせる高得点化する勉強をする時期に至った。特にこの時期に必須な行為が不得意科目の過去問解法を体得する勉強。
それは何故か。言うまでも事実だが、貴方が喩え得意科目群で満点を取ったとしても、不得意科目が科目の合格基準点つまり足切り点を満たせなければ不合格となるからだった。合格を目指す試験の合格基準がそう規定しているのであれば、貴方がその基準に異論を唱えても国家試験はそう言うものだから仕方ない。
「これだけ本」には手を出すな
そこでありがちなのが、「○○試験対策これだけ要点集」と本試験に対する即効性を喧伝したアンチョコ本に手を伸ばす行為。確かに書籍として販売されるものだから効果のない詐欺的なものでない。しかしそれが貴方にピッタリで効果的、これだけであるかどうかは別の話だ。想定読者の多くに広く浅く書かれている本だからだ。
かつ貴方がこの時期に行うべき勉強は、貴方特有の弱点、特に苦手科目のそれを徹底的に解消すること。だとすると、上記の「これだけ要点集」の類が貴方にとって「これだけ」で済むと考えにくい。一般的なその類に手を出すよりも、貴方特有の弱点を示すものに沿って連休後半に徹底的な勉強をすることが得策であると想定できる。
では、明日からの勉強に集中できる期間、そのような勉強はこれをどのようにしてできるのか?合格を目指して連休後半を有用にする勉強法をご案内しよう。

結 論
それが朝活勉強法から始める高質量の徹底勉強。朝活勉強法はご案内の通り。休日だからと睡眠負債の償還に励むのではない。休日だからこそ早起きして午前中から勉強に集中する。後者は過去問の解法の理解を深めた質と過去問を繰り返し解く回数を高めて量を確保する勉強を徹底して行う。特に不得意科目でこれを実践する。
その目的は不得意科目で、特に苦手な例えば受験生の多くが敬遠しがちな計算問題など項目に関して、科目の合格基準を確実に満たせる基礎固めをする。こうして、連休明けの日々で得意科目で得点を稼げる勉強にも安心して取り組める勉強の体勢作りをする。つまり今後に於ける貴方の資格試験の合格を確実化すること。
何故ならば、「不得意科目ってギリで良くネ」とする受験生はギリの勉強をしたが故に、試験問題によくある難易度の多少の変化にも追従し難い。結果「あんなムズイ出題って聞いてないヨ」と苦汁を嘗めることが多い。その様に合格することに不確実な状況を解消する為に朝活勉強法から始める高質量の徹底勉強が有用だからだ。
高質量の徹底勉強の取り組み方
それは一級建築士の受験生を例にするとこうだ。その多くが苦手としがちな試験科目は構造。特にこの計算問題である。一方その問題を克服つまり得点できるようになると、総点の相対評価で合否を決める本試験でそうできた受験生は合格しやすくなる。30問中に5~6題/年で10年分の構造計算その仮に60題の過去問を対象にする。
以上の背景として、受験生は構造の30問と施工の25問、その合計55問を2時間45分(165分)で解く。即ち3分/問で正答を目指す。確かに計算問題をその時間で正答することは困難。だがそのことは可能だ。仮にそれを三倍の時間配分で9分/題×6題で54分で正答を目指す。残す49問を111分でつまり約2分/で解答とする。
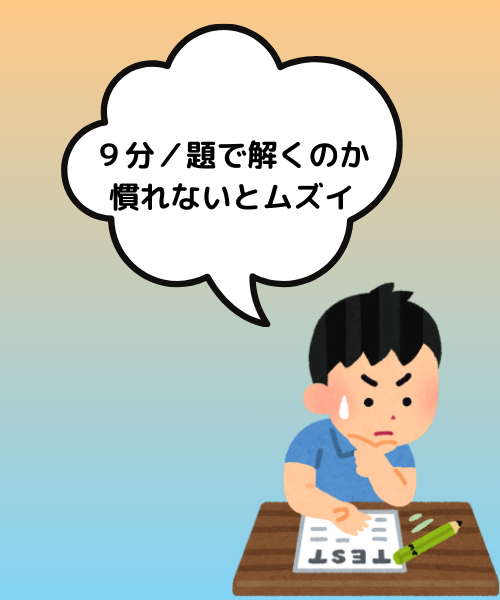
残り49問の殆どが暗記問題だ。その要点を暗記できれば決して正答することに困らないと想定できる。またそうでなくては安心して苦手とする計算問題で集中して正答を目指す事が困難となる。しかし暗記問題は計算問題に比してこの要点を只管に覚えれば克服できる。以上から、構造計算の過去問対策を次のように高質量で行う。
苦手項目を高質量の勉強で克服する
さて、標題のようにする対象は、前述した構造計算の過去問で、6題/年×10年として60題だった。1日目はこれを9分/題で解くと540分で、6問解く毎に6分の休憩を取る。結局10時間を要する。その後、夜に答え合わせをして、誤答した問題の解答解説を読解して理解を深める為に要約もする。これで1日目を終えるとする。
そう耳にすると「ゲッ10年分の計算問題を解くって無理」と反発したくなるだろうか。だがそれは早計だ。夏期の本試験までに僅かに数ヶ月とする今、10年分のそれであってもその全てとは言わずとも、その一部を解いているはずだ(そうでなくてはこれ以降を読み進める意味もない)。よって「ゲッ」のように大変でもないはず。
2日目は前日に誤答した過去問を同様の所要時間で解く。前日の解答解説に関する読解と要約が正しく行えていれば再び誤答する過去問も減るはず。答え合わせをして再び誤答した過去問の解答解説を読解してこれを再び要約する。時間に余裕があるはずだから、二度目の誤答をした弱点をを解消できるように参考書からも学習する。
1日目よりも時間的な余裕が生じる(正答率を高めることを目的にして1日目で解答解説を読解した)はずなので、その余裕を使って仕上として誤答した計算問題を白紙を使って解こう。その正解に至る過程を完全再現することが正答への理路を想起することであるから、解法を理解の元で記憶することに大いに有用だ。
3日目は前日に以下同文。三度目の誤答をするのは基礎の知識や技能に何か欠落があるはずだ。それを素直に認めてその欠落を補完できる知識や技能を参考書からも繰り返し正しく学び取る。誤答問題の解き直しと答え合わせ、誤答した問題に関する解答解説の読解と要約を繰り返す。以上、苦手解消の回数・量と理解・質を高める。
2日目よりも時間的な余裕が生じる以下同文。要するにこの3日間で苦手項目の過去問を繰り返して解き、誤答を招く弱点つまりそれの原因たる知識や技能、それらを徹底的に補強する。こうすることが連休後半の3日間で行う高質量の勉強だ。つまり不得意科目の苦手項目をこの3日で克服する。またはその手掛かりを掴むのだよ。
無理をせずに無理ができる勉強法
「えっそれって無理」と早とちりしてはならない。10時間/日とすれば3日の連休でそれが可能だ。朝活勉強を7時から12時まで5時間、13時から18時まで同時間として10時間/日なのだから。更に夜は19時から22時まで3時間の勉強もできる。特に1日目は夜間を答え合わせと解答解説の読解に当てれば次の日に余裕を持てる。
初日の午前と午後で60問の全てを解いて、夜に答え合わせをして解答解説を読解し要約する。2日目に1日目に誤答した問題を解き直し解答解説を読解してその要点を要約する。夜、また誤答した計算問題を解き直す。3日目に更に二日目の解き直しで誤答した問題を解き直し以下同文。こうして計算問題を高質量の勉強で克服する。

「でもそればかりじゃ飽きちゃう」であるならばこそ、食事休憩の際に得意科目で視聴覚学習などをするのはどうだろうか。集中力を維持する為に、1問当たりに9分として1年分の計算問題6問を解いたら6分の休憩を取る流行のポモドーロ技法を使おうのだった。休憩中に耳から暗記科目の要点を学習することもできる。
勿論、上記の時間構成は受験生各人の裁量で自由にできる。今まで先延ばしをしていた不得意科目の苦手項目を明日からの連休中に高質量の勉強で解消する。最低でも苦手科目の苦手項目を解消する目処を立ててはいかがだろうか。試験本番までの暦を考えるとそれが可能な好機は明日からの三日のようだがどうだろうか。
連休後半で高質量の勉強に健闘を祈る。
Good Luck!