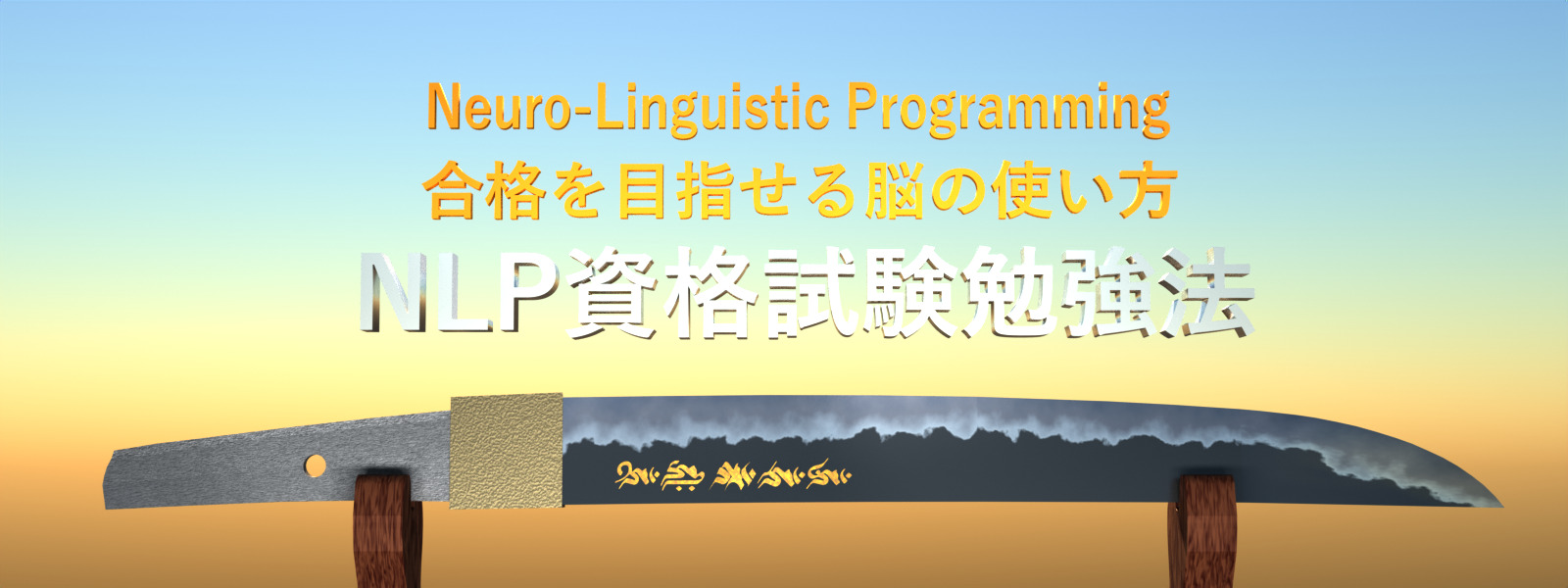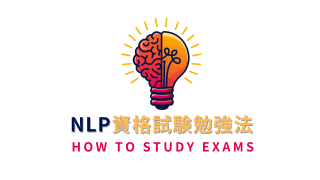「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年3月21日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
多忙な毎日の勉強時間はどうですか
こんにちは近藤哲生です。「ふぅ忙しい」と呟いてしまう。その様な自分にふと気づくこの頃では。だって今って年度末でしたね。暦は今月も下旬を示し期末の締めに備えて大忙しでしょうか。「それって関係ない」とお感じの方は慢性的な多忙で時期的な変化を感じる暇もないと言うのが現実なのかも知れません。
いずれにあっても、その状況下で仮に今夏の受験を控えている受験生であれば、言うまでのもなく受験生としての本願を叶える為に、苦手科目は合格基準を上回れて得意科目は総点のそれを同様にできる、即ち合格を目指せる試験勉強に励みたいはず。ところがこの時期にもそうする事に対する困難が行く手に倒木の様に横たわる。
受験資格を得られる時期によくある不条理
ではその一例。大手ゼネコン勤務、大卒2年目のS君、建設現場にも慣れて、その統括所長から様々な仕事を任される。「おいS君あの手配はどうした」等とことある度に急かされる。その一方、一級建築士の受験を今夏に控える。様々な利点から何としても合格した。だが多忙さから勉強時間が不足しがちだ。
残業が普通で、遅くの帰宅後でも、どうにかして励みたい勉強だが、仕事の疲れで問題集を開いて間もなく強烈な眠気に襲われる状態で集中して勉強する事もままならない平日。勉強ができるはずの休日は平日の疲れから昼近くに起床するのがやっと。早起きしての勉強もできずに、受験勉強の進捗に焦りを禁じ得ない。

その状況は他の業界にある受験生にあっては似たり寄ったり。受験資格が得られる業務経験をする時期の受験生は、仕事にも慣れて多く任される(押しつけられる)頃でもあるので勉強したいのにそれが思うに任せない状況にあっても不思議ではない。だって資格試験、受験資格を得られる時期の人たちはそれが普通だから。
先の如くに世の中は誠に皮肉なもの。だが、それを嘆いてているだけでは、資格試験に合格する為に必要だとされる勉強時間からして、それに相応しい勉強時間を確保することはなかなか難しい。やれやれどうしたら勉強時間を確保することができるのか。今回は合格を目指せる勉強時間を確保できる一策を確認してみたい。
結 論
その一策が休日に10時間以上の勉強をする習慣だ。週末二日間が休日だとして最低でも合計21時間の勉強だ。その時間は週平均で一日3時間。例えば初受験で一級建築士に合格を目指す人が一日に最低でも3時間の勉強を毎日すべき条件を満たす。平日、多忙と疲労から、勉強する事がままならない状況を解消できるからだ。
併せて、勉強を週末だけする様に時と時の間に行う学習が忘却に晒され無駄になる現実からして、平日に例えば通勤の往復1時間毎に、併せて2時間の勉強をすることが勉強した内容を記憶にすることに有意であるから肝要である。これを前提にして前述の勉強時間を確保することが合格を目指せる勉強時間の確保に有意となる。
資格試験の合格が求める試験勉強の時間
他の例えば公認会計士などの資格試験でも合格する為に必要とされる勉強時間は最低でも千時間を超える。上記のように3時間/日として1年間、365日で勉強できるとすれば、合格に資する勉強時間として1095時間を確保できる。「それって無理」と嘆いても、資格試験の勉強はそうするものだから仕方ない。どうだろうか。
もちろん「オレ・アタシは質で勝負するからそんな長時間に勉強しなくても合格できる」と考えかもしれない。しかしそれは勘違いだ。上記の勉強時間はただ勉強するのでなくて、言うまでもなく上質に勉強した状況における千時間以上だ。ただ多くの勉強をすれば難関の資格試験に合格できるのであれば合格を目指す受験生の誰もが苦労はしない。
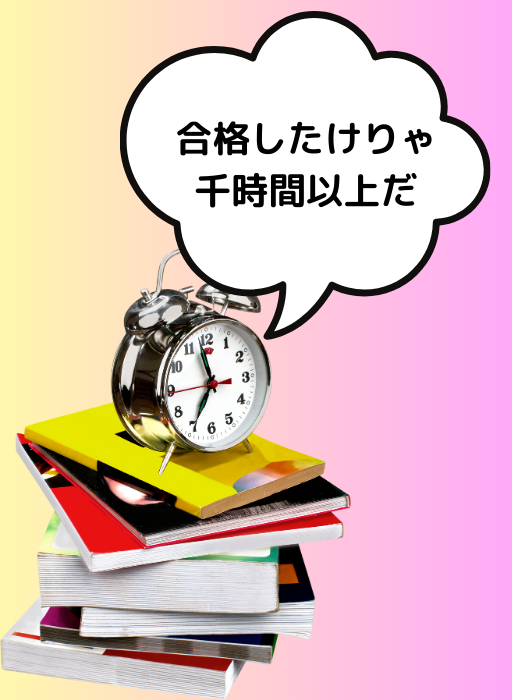
量より質に潜む現実とは
加えて「量より質」と勉強に関して言われるが、その前提である質をもたらす要素が実は量だ。その量は、例えば問題に誤答した結果がアドレナリンなど苛つき不快なストレス神経物質を生成する状況を解消しようと、脳が自身の神経組織に可塑性を発揮して失敗でなく快感を得られる成功を学習する為に必要だからだ。
上記に対して「そんな沢山の失敗をしたら勉強が嫌にナンネ」と異論があるだろう。勿論、そのご指摘は当を得ている。だから、失敗をするにしても、試行錯誤を繰り返す過程で取り組み次第で成功できる細分化した失敗を繰り返すことが大事であることはご案内の通り。上々に難易度が高くなる問題を解くようにする訳だ。
以上のように細分化した失敗を多量に繰り返して成功することを学ぶ過程は自ずと時間を要する。この結果として同じ失敗をしない学習結果としての質をこれを行う学習者に生成する。例えば野球やテニスの選手が多量の素振りをしたり楽器演奏者が同じ楽節を繰り返し練習したりする訳は上記の量が質を生成する仕組みに存する。

以上から「量よりも質」と量をこなさずに効率的な勉強を夢想することよりも、脳神経科学的な根拠からしてまずは「質よりも量」で勉強する為に冒頭の休日10時間以上の勉強を実践する事を推奨した。そうした量がその実践者にもたらす質はこれが徐々に生成されるに従って、合格点を獲得させる勉強の質量を受験生に構築する。
平日にできることは休日にもできる
だが「それって無理かも」とご懸念と拝察する。しかし本当にそうなのだろうか。平日、9時から5時まで、かつ3時間の残業が当たり前の職場に貴方がいるとしたら、その労働時間は10時間を超える。現実的にその長時間労働をこなしている状況からして、休日前日に早々の就眠をすれば同様の勉強時間が無理でもないはずだ。
と言うと、「休日にそうしたくないから平日に睡眠時からを削って勉強するわ」とお考えだろう。だがそうされることは決してお勧めしない。第一に仕事の疲れを覚える状況で深夜まで勉強する事はそれこそ質の確保ができない。第二に学習を記憶に定着させる為に最低でも7時間の睡眠が必要だ。つまりその勉強が非効率だからだ。

また、寝る子は育つ一方、寝ない大人は肥る。睡眠不足と様々な生活習慣病を誘発する肥満が相関する結果を睡眠学は指摘する。本邦は大人の平均的な睡眠時間が6時間と諸外国に比して短い。高血圧や糖尿病、心疾患や脳血管疾患などで悩む人を多く抱える。このように睡眠時間を削る習慣、勉強は不健康への捷径でもあるのだよ。
休日の勉強を10時間超えでできる時間割
さて、休日に例えば11時間の勉強をするには、以前にご案内した朝活的な勉強から始めよう。例えば朝6時に起床した後に集中した勉強ができるように幾つかのルーティンと朝食を済ませて7時から、適宜に休憩を挟んで四時間半、午後は1時から6時まで同様にして同時間、夕食後に二時間、それぞれに勉強をすれば事足りる。
先の四時間半は苦手科目なら50分の勉強と10分の休憩、得意科目なら55分の勉強と5分の休憩、そうした学習効果を担保できる脳神経科学的な根拠に基づいた時間の細分化手法から、そのような組みあわせを工夫すればこれを確保できる。注意、その休憩時間は決してスマホを弄ったりして休憩の学習効果を棄損してはならない。
脳は外部刺激を少なくしたその典型である睡眠状態に於いて学習で獲得した情報を記憶として定着させる為にその内容を遡及して自動的な学習を進める。この仕組みから勉強の休憩時間も同様に外部刺激を遮断した状況を得ることが、勉強した結果を記憶として定着させる為に有用であるから、スマホなどに触れずに何もせずに休憩するのが賢明だぞ。
であるから合格を目指しそれを確実にする為、休日に10間を超える学習時間の量を確保するのであれば、これの質を確保する為にも、これまたご案内の通りに、スマホやテレビなど悪鬼の如くして貴方の意欲や集中に悪影響を及ぼすモノどもを勉強の環境から遠ざけることが極めて大切であることもクドクドとここに大書きしておく。
休日10時間以上の勉強に健闘を祈る。
Good Luck