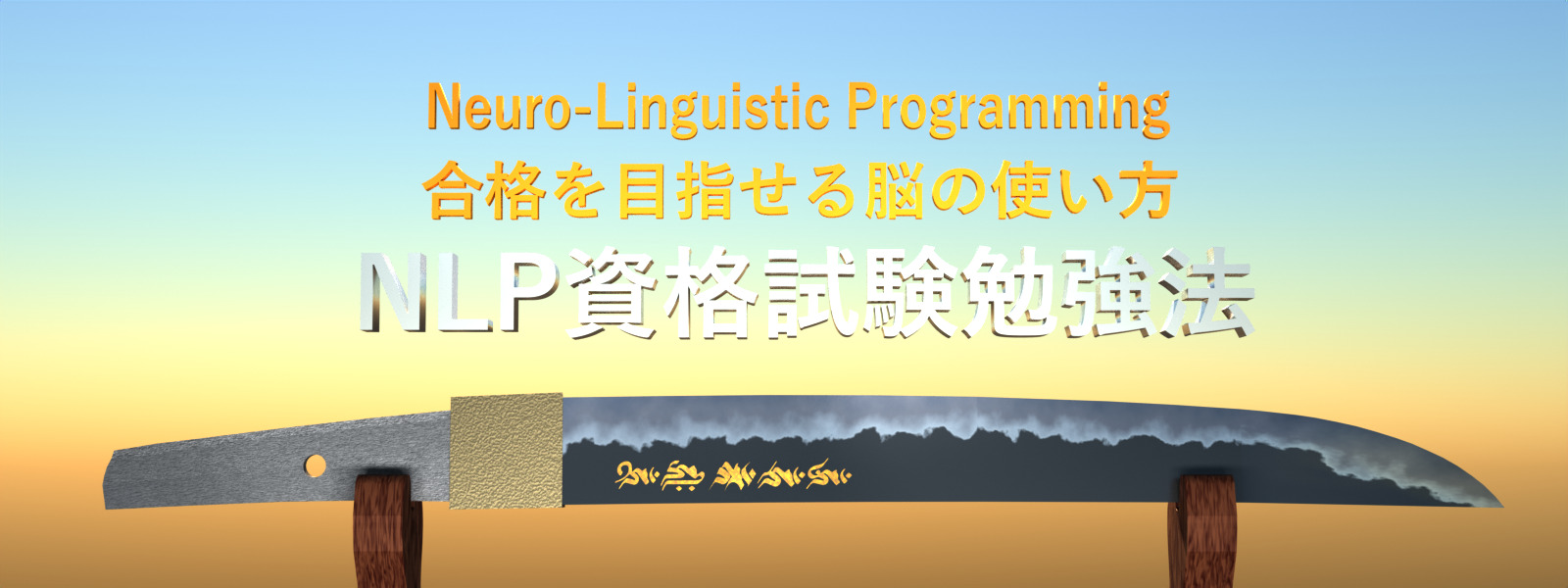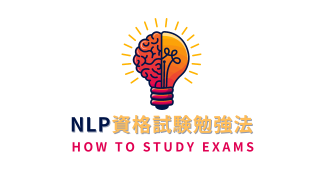「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年9月12日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
時間泥棒の発見はどうされましたか
こんにちは近藤哲生です。前号は二段式で勉強時間を増やす為の方法をご案内。資格試験で合格を目指す為に必要な資源はいずれにしても時間です。これがなければ効果的な勉強法を知ったとしてもそれを活用できない。逆にそれさえあれば有用な勉強法を実践して着々と合格を目指せる。その時間を確保する為の二段式でした。
以上の二段式から私たちは勉強時間と集中力も確保できる。
では、合格を目指せる勉強はどうしたらできるのか。例えばこう。
「過去問を繰りかえし解く?!」
「参考書を地道にコツコツ読む!?」
「動画教材を徹底的に見聞きする?!」
確かに、そのどれもが合格を目指す為にある事を満たせば有用です。しかし、そのある事が欠落すると「・・・したのに」過去問の正答率や模試の得点が上がらずじまい。「あんなに勉強したのに不合格だ」と憤る無用さに転じる。実は前述したある事が、試験勉強の核であるデシラの解消に必要なのだから。ではある事とは何か。
デシラの解消を加速する視点転換勉強法
それは様々な立場・視点からデシラを発見して、デシラを潰していく勉強法。その視点は例えば過去問の作成者や参考書の筆者、そして動画の講師の目線。デシラは試験に頻繁にデる分野で自分がその解き方をシラない項目。潰すはデシラをデ知るにすること。この背景は効果的な学習の研究が発見したピラミッド型の階層。
多くの人が取り組む下の層は受け身の例えば講義を聴講しただだ本を読んだりする学習定着率が5から10%の勉強。最上層は少数の学習者が実践するその率が9割の学習法。これが教える立場・視点(共著はティーチングと呼称した)で行う勉強法だ。対して「アタシは教える人なんていないのっ!」との不満を想定できる。
だがその気持ちを抱くのは早計。実はその人、24時間365日、貴方の間近にいる。ご賢察の通りにそうご自身である。だから、オレが知らない分からないそれらの項目や解法をオレに教える。それらの不知を知り、それを既知にする為に不知はどのようにして既知にできるか。その理路を自身に教える(即ち言語化する)。
視点転換勉強法の取り組み方
その取り組みは次の3段階を繰りかえす。
1.第1の視点、不知を知る
2.第2の視点、不知の源を認識する
3.第3の視点、2に立脚して1の視点者に教える
以上の段階をステップバイステップでもっと言語化しよう。
1.不知を知るは決して難解でない。参考書を読んだらそれが提示する例題を解く。視聴覚教材を見聞きしたらそれが出題する問題を解く。それらがなくともお勧めできるのは、過去問の組み合わせから7~8割が出題される資格試験の特質から、過去問を解くこと。
それらに解答して、自らの正答や誤答を確認する。
ご注意。ご自身の不知を知ることで自らを責めたり叱ったりする行為はその一切が無用。その様な行為に耽る暇があったら、次の段階は不知の知を明確にすることから、これに進むのが得策だ。そられの問題に誤答しら「間違っちゃった」や「その内に解き直そう」で決して終わりにしない。そうでなく第2の視点に進む。
2.は貴方の相手つまり出題者、採点者だ。何をどのようにして誤答したのか、何を覚えていなかったか、どのように知らなかったのかと問を己に向けてその告白を通してご自身自らを観察する。初学者ご本人は知らない解らない項目の多さにウンザリする。再受験を目指す人はまだあるそれら多さに憤るかもしれない。
3.は1と2との双方が視野にある第三者の視点。解答者と出題者の両者を観て不知の知にある自らに不知を既知に転じる知識や技能を教える立場つまり解答解説者や予備校講師だ。または参考書の著者となる役割を演じる。何を教えたら、第1の視点にある私は面白さやスッキリ感を覚えるかを考える。その知見を言語化する。
建築基準法を事例に視点転換勉強法の橋頭堡を構築する
一級建築士の受験生、その多くがデシラにする法文が(建蔽率)第五十三条(以下、本条文という)だ。この条文は読み流す者を誤解に誘う難所をたんまりと隠し持つ。だから、出題者に多彩な設問を創らせてくれる実に美味しい条文でもある。これに関する過去問を解き、これの解答解説を読むと例えばこうある。
「法第五十三条第三項から建蔽率は十分の六で~」と設問から正答を導く理路が展開される。その解説は限られた紙面に於いて要点を要領よく簡潔に説く立場から、その項を解答者が読解できることを前提に記される。受験生はその解説から本条文が未知でも既知でも本条文第三項を読解しにかかる。「同項各号ってナニ」となる。
その条文が「前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては【同項各号】に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする」だ。
第五十三条第三項の同項各号を事例とした正しい法文解釈法
「同項各号」の結論は「第三項」だ。決して第一項でない。条文は一見第一項の数値を指すように読める。だが、法文の形式的解釈法から「各号」は第三項に属する第一号と第二号を指す。あるAIは「同項各号」を第一項と誤解した。理由は「数値が第一項にしか存在しない」とした機能面に引きずられたためである。
しかし法制執務の規則は「同項=その項」であり、条文の慣用表現からすれば誤り。この誤読は何もAIに限った現象で決してない。建築士を目指す基準法の学習者も陥りやすい。別のAIも同様に第一項説を採ったが、後に修正した。理由は文理解釈における基本規則を軽視したとの認知。ここで重要なのが次の点だ。
文脈上の便宜や結果の合理性ではなく、条文そのものが採る形式的指示語を優先すべき点である。法文は形式にそってご案内の通りに漏れなくダブりなく記述される。上記の「文理解釈における基本規則」とは、法律文の日本語の用い方に従うという意味である。例えば「前項」とあれば直前の項を意味する。
上記から「同項」とあれば今まさに読んでいるその項を指す。これらを形式的指示語と呼ぶ。数値や条件がどこに書かれているかに惑わされず、まず言葉の指し示す先を正しく特定することが基本だ。加えて、「前二項」は第三項を読んでいる場合は、項を一つずつ遡及して二項と一項とを意味する。
法規の学習は文理解釈、形式解釈と機能的帰結を分ける
確認しよう。まず「同項各号」は第三項の第一号・第二号を指す。異なる項であれば例えば「第○項」と先の文理解釈から記される。次に、それらが条件規定であり数値を持たないため、加算の対象となる数値は第一項各号にあると整理する。この二重構造を理解することが法文解釈の鍵である。
法規の学習はこれにおいては形式解釈と機能的帰結を分けて考える。疑問点の前後を先の用語規則から1つ1つ読解する。この姿勢こそが誤読を防ぐ最良の方法である。「第一号【又は】第二号」「第一号【及び】第二号」の【又は】と【及び】も極めて重要だ。「用語規則」によって1つ1つ読解する。これが法規の学習の要だ。
不知を既知にしたらやるべき視点転換法とは
それが先の解釈法とその方法から得た既知を不知だった過去の自分と言う他人に教える学習法だ。既知を得た貴方自身は他人に教えられる不知の知にあった第1と不知の知を深めさせた第2、他の人を無知から既知にした経験をした第3の視点を有している。よって既知を深く広い知見にできる機会を得た。
それを自らに説明しよう。目の前に置いた消しゴムやノートに書いたキャラを不知にあった自分と見立てる。一人語りで、自らが得た知見を過去の自分に講義をしよう。一人レクの準備にキーワードだけを紙に書いてもよい。それを見ながらレクする。出力が最良の入力になる。正しく言語化できない自分に直面するかもしれない。
そうであっても、自分を責めるのは不要だ。また自らに存在した不知の知を得ると言う絶好の学習機会を得たからだ。であるならば、また1から3まで繰りかえそう。視点を変えて、不知の知を自覚しそれを深め、そして不知の知を既知に変える過程を加速し深化できる言語化の立ち位置、教える立場に立とう。
視点転換勉強法に健闘を祈る
GoodLuck!