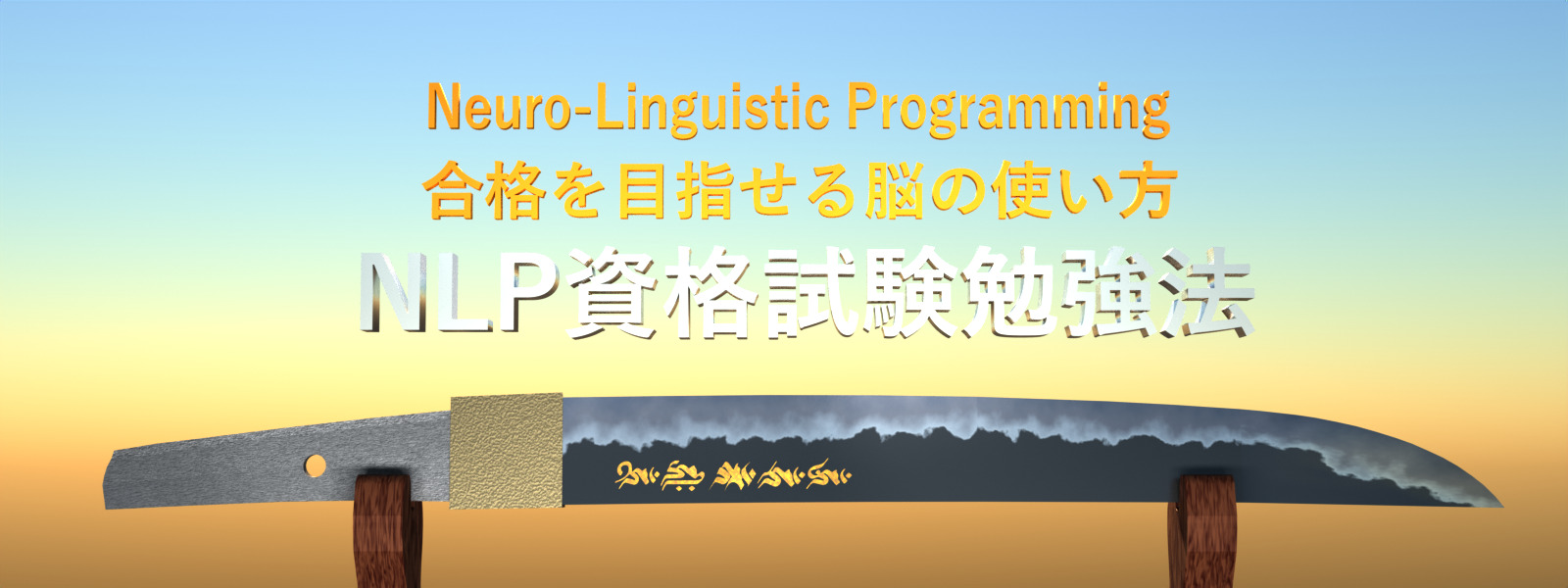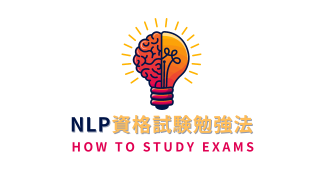「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年11月14日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
要点をテストで出力する勉強はどんな調子ですか
こんにちは近藤哲生です。前号、参考書や法令集の試験に頻出だから体得したい要点をより確実に覚えられる、つまりそれを脳に入力する勉強法として、記憶が想起つまり思い出すことで強化される脳神経科学の背景から、その要点をテストして脳から出力する方法をご案内。それは勉強が得意な人の習慣で試験勉強の要諦でした。
その勉強法は端的に言えばテスト中心の勉強法。テキストを読んだらそれを読解できた事を検証する為に例題を解く。誤答した過去問の解答解説を読解したことを確かめる為に時間をおいて同じ過去問を解いてその理解度を確認する。その様に想起つまり脳から情報を出力する過程で得点に関わる要点の記憶が強化できるのだった。
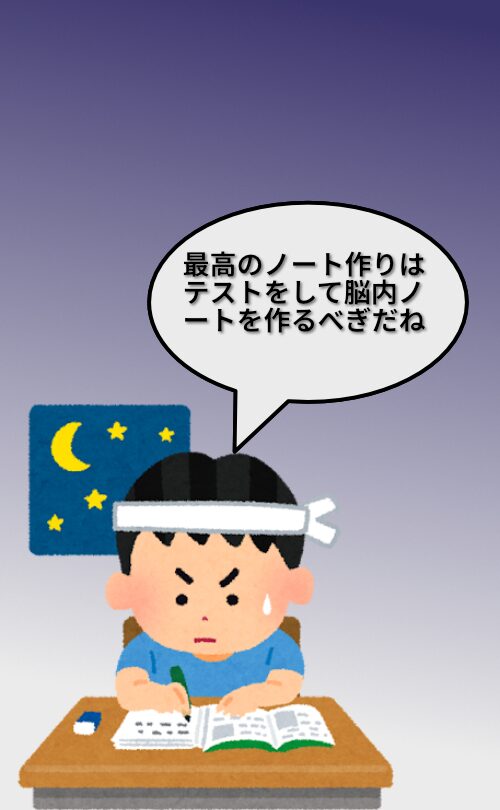
テスト中心の勉強法で頻繁に到来するお悩とは
それが続いて例示したテスト中心の勉強法に関する声。
「その勉強法だと誤答続きでめげる」
「その勉強をすると弱点ばかりが目立って嫌になる」
「その勉強を続けていると自分の正答できなさにイラつく」
確かにそのお悩みは実に切実。その気持ちは察するに余りある。
その一方、その状況は呪わしくもあるが祝福でもある。受験勉強中の体験であり決して本試験中の経験でない。前者であるから後者に至るまでに方法と努力で改善の見込みがある。後者であるならその状況からして多分に合格は困難だ。改善の余地が全くない。それを祝福というよりもむしろ合格を目指せる予祝と言える。
できない嘆きに浸ってはダメ訳
勿論、「できなさの何が予祝だ、合格への前祝いなの」とお怒りの向きを想像するに難くない。例題や過去問を解く度に×だと嫌になって当然。そのお気持ちは合格まで長期を要した期間にその状況に沼っていた経験からして昨日の事のように解る。しかし、その気持ちに浸っているだけでは予祝でなく呪いに居着いてしまい兼ねない。
人は何かに居着くと恒常性の維持からそれが良くも悪くも(己を制限するものであっても)それを保持する。例題や過去問を誤答してしまう状況が続くとこれを能力改善の好機と捉えずに例えば「オレ・アタシって(何を基準にこうなのかが無根拠の)駄目な人間なのだ」と固定観念を維持して活力を損なう自らへの呪いとなす。
その状況を好機に変えるには、テストの度に誤答をもたらす要点や解法に関する結果的に誤解(解ったつもり、理解できているはず)を理解した(解き方が絵になったや要点が腑に落ちた)と言える状態に転じることが必要だ。では、それらに関する誤解を理解に転じる為の根本である参考書や解答解説の読解はどうすればできるのか。
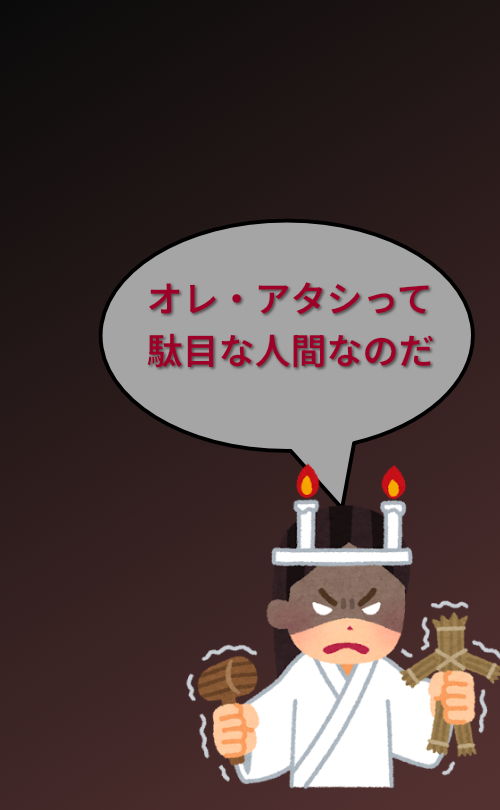
有用な読解はこれをどう行うと言われたか
まず読解は「文章を読んで解ること」と意味づけされる。だが、その意味づけはこれを表記した前後の文字を言い表しただけ。理解が「話の筋(理)を解ること」と言われることに似て何をどうしたら、読解したと認知できるのかをこの文字面は教えない。加えて、「よく読むことよ」「丁寧に読めば解る」と言われるのがオチだ。
そもそも上記のように抽象的な説明で読解を息をするように行える人たちは、何を・どのようにして例えば得点力を基礎付ける要点の獲得に記す参考書や解答解説の読解が可能なのかが暗黙知・非言語として蔵する。読解ができる事が当たり前であるから、「よく・丁寧に読む」事をして有用な読解を行うことが自然にできる。
その人たちは世に言う「秀才」である。幼少期から多読を通して読書ひいては読解を身体化している。結果、「繰り返し読めば解るの」「要点を見かける様に読むんだよ」と発言して、「それで読解できれば苦労はしないぞ」と凡人達をムカつきに誘ってくれる。一方、試験の切迫に伴って凡人が模範にするのは次の事態に陥る。
凡人がハマりがちな読解したつもりとは
でだ、「よく」や「丁寧に」を「それってどうするの」と問えばその答えは「何回も読め」「要点に線引きしろ」「要点をマーキングするの」となる。確かにそれらの方法は学生時代に皆さんもご体験で頷けるだろう。しかしその効果は定期テストの度に「あれほど教科書を読んだのに」と失望の得点をもたらしたはずだ。
それもそのはず、海外の学習に関するメタ分析が解明した結果からすると、繰り返し読みや線引きそしてマーキングは極めて読解が目指す理解に関して決してコスパが宜しくない。むしろ、テストの結果からして解ったつもりにさせるだけの悪法だ。勿論、「秀才君は同じことをして何時もクラスで1番だったケド」と疑問がわく。
では凡才と秀才との違いを創る違いは何か。例えば「結局さ地頭の差よね」と思える。だが実はそうでない。後者は凡才と同じ行為を行うがそれの基盤が既に理解にある。理解した結果を繰り返し読みや線引きやマーキングにするる。逆に凡人のそれらは未だ理解に基礎がない。且つその基礎である理解を形成する効果が乏しい。
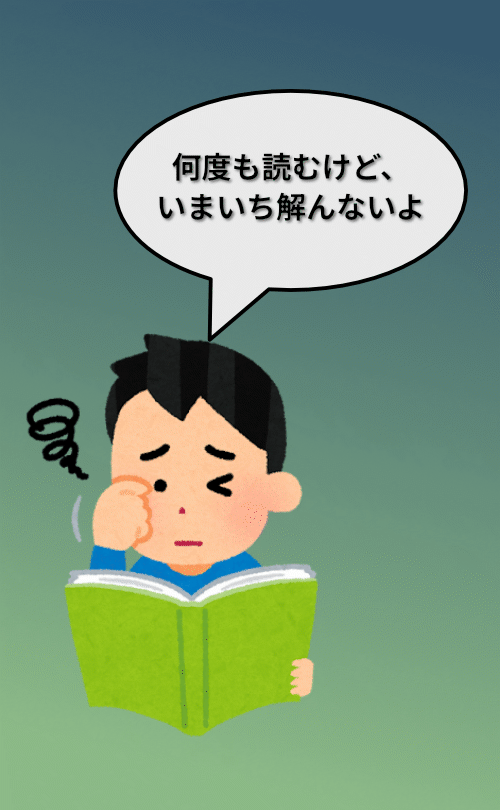
読解を検証できる具体的な言動とは何か
以上の如く凡人と読解との関係は無残な逆接を呈する。それらが密接になるほど効果の薄さからして時間を浪費する。では、読解(文章を読んで理解した状態)の適否を検証できる方法は何か。それが本誌でご案内の通りである言語化だ。理解は思考の一形態であり、思考は言語であるから、その方法は言語化つまり言葉にした様子だ。読解で得たと思える要点を要約・言い換えできる言動だ。
例えば投資の文章を読解したとする。未読解の者は「投資って将来のお金を増やす為に今のお金を何かに投じること」と読み取った言葉の定義を述べたり同語反復をしたりする。読解者は「投資は負債や純資本の現金を株や不動産に資産に換えて、その資産が生み出す利益を獲得する行為でリスクをとる活動だ」と言える。
勿論、言葉の定義を言えることは決して無駄でない。むしろ読解の基礎であるから最低限に読解に関して必要だ。だが、読解の結果である理解は、それを基礎として「何がどうしてどうなった」と事例と根拠とその結論からなる話の筋を解っている。だからそれを負債や純利益と現金の関係を言える様に自らの言葉として発し得る。
読解の深度を貴方も深められる方法はコレだ
以上に「自分の言葉でイチイチ説明するのってニュース解説者じゃないから無理」「それってコメンテーターじゃないからできない」との異論もあるだろう。ならばもっと簡単でより具体的なイチイチ言語化せずとも、参考書や解答解説の読解を即座に検証できる方法を提示する。それがテスト、例題や過去問で正答を目指すことだ。
自らの言語化(読解して得た要点を具体的に説明する)にしろ言語化を省いてテストをするにしろ、読解から期待される理解を検証する為に要するには、繰り返してご案内の通りテストで出力することだ。誤答した例題や過去問の正答に役立つ参考書や解答解説を読解して理解できたと思えたらテストの結果でその思いを検証する。
その検証の結果、誤答を繰りかえしたら読解でなく誤読だ。正答を果たせたら誤読でなく読解であると評価して大過ない。誤答は要点の忘却からも生じるが有用な読解は記憶を強化する理解を生成するから、読解で得た要点を忘却することがほぼあり得ないからだ。読解が読んだ文章の論理を解した場合に理解と記憶は相関する。
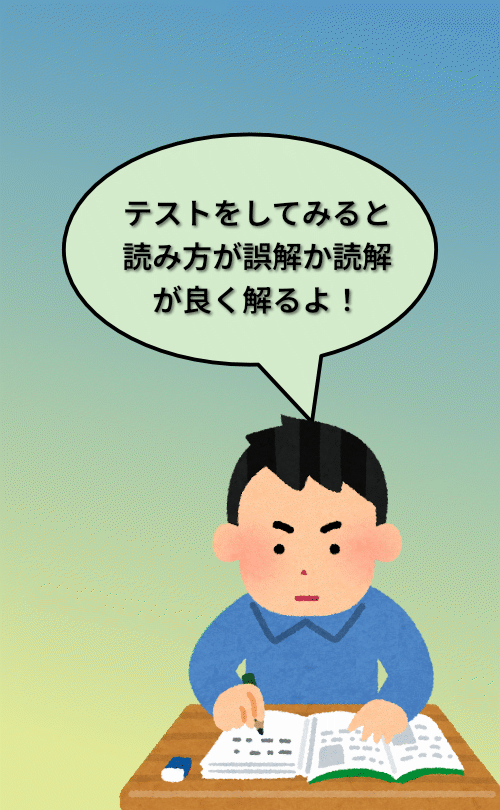
論理は事例とこれを挙げる根拠と以上からなる結論が織りなす物語だ。物語は古来語り継がれた事実からして人を忘却から救出してきた。つまり記憶を確固にしてきた。この洗練された一形態が論理だから、読解の過程で「何が(事例)どうして(根拠)どうなった(結論)」と論理を解するとこれに関して記憶が強化される。
いずれにしても、参考書や解答解説を誤解でなく読解する為に有用な行為は出力(自分の言葉で具体的に説明したりテストしたり)することだった。この結果が検証して正しくなければ読解をやり直す。正しければ次の読解に進む。勿論、直線的に進むことはない。三歩進んで二歩さがることもある。地道にコツコツ取り組まれたい。
検証つきの地道な読解にも貴方の健闘を祈る
GoodLuck!